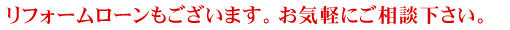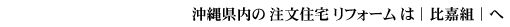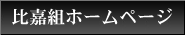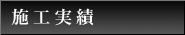六可の原則
どの職場でも、報告・連絡・相談の必要性は、十分に認識されているようです。
ところが、その伝え方となると、要領を得ていない人が少なくありません。要点を押さえた伝達手段として、よく使われるのが「六可の原則」です。
「WHEN」「WHERE」「WHO」「WHAT」「WHY」「HOW」の5W1Hと言われるものです。これをイギリスの小説家で詩人のキャップリンダは、「六人の忠実な召使」と名づけて、自らの詩作に活用したと言われます。
まず、自分が伝えたいことは、報告・連絡・相談のいずれかを、明確に相手に示します。そして「何時」「何処で」「何人が」「何を」「何故に」「如何にして」という、5W1Hに即して話せば、相手にスムーズに伝わります。
反対に、これらが明確でない話は、相手に伝わりにくく、誤解を招いてしまう場合もあります。
業務上のやりとりを円滑に進めるために、「六可の原則」を念頭に置いて、会話をしていきましょう。
今日の心がけ…六可の原則を心がけて話しましょう
職場の教養(倫理研究所発行)8/3~
ところが、その伝え方となると、要領を得ていない人が少なくありません。要点を押さえた伝達手段として、よく使われるのが「六可の原則」です。
「WHEN」「WHERE」「WHO」「WHAT」「WHY」「HOW」の5W1Hと言われるものです。これをイギリスの小説家で詩人のキャップリンダは、「六人の忠実な召使」と名づけて、自らの詩作に活用したと言われます。
まず、自分が伝えたいことは、報告・連絡・相談のいずれかを、明確に相手に示します。そして「何時」「何処で」「何人が」「何を」「何故に」「如何にして」という、5W1Hに即して話せば、相手にスムーズに伝わります。
反対に、これらが明確でない話は、相手に伝わりにくく、誤解を招いてしまう場合もあります。
業務上のやりとりを円滑に進めるために、「六可の原則」を念頭に置いて、会話をしていきましょう。
今日の心がけ…六可の原則を心がけて話しましょう
職場の教養(倫理研究所発行)8/3~
注文住宅 リフォーム 沖縄 |比嘉組|
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。